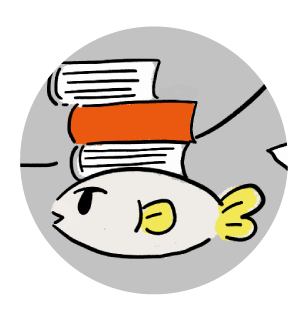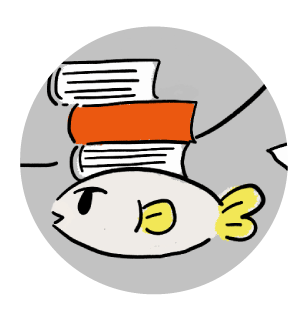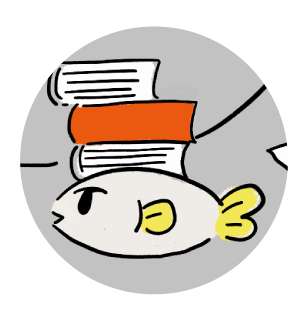-

北岳山小屋物語/樋口明雄
¥850
出版:山と渓谷社 発売:2023年7月 定価:1100円+税 文庫サイズ・376ページ ================== 大藪春彦賞受賞作家・樋口明雄が描く初のノンフィクション大作! 南アルプス北岳周辺にある5軒の山小屋(白根御池小屋、広河原山荘、北岳山荘、北岳肩の小屋、両俣小屋)の日々を描くノンフィクション。 小屋開け、山岳遭難救助、山小屋生活の日常、小屋番の素顔など、宿泊・通過するだけではわからない、山小屋の裏側を描く。 単行本刊行後、それぞれの山小屋では、経営の変動、管理人、スタッフの異動、小屋の改装や建て直しがあった。 これらの変化について追加取材、加筆し文庫化。

-

進化しすぎた脳/池谷裕二
¥500
出版:講談社・ブルーバックス 発行:2007年 定価:1000円+税 11.4 x 1.9 x 17.4 cm・304ページ AIによる書籍紹介 ================== 脳の驚異的な進化とその可能性を探求した一冊。 著者は神経科学の第一人者として知られ、脳の仕組みと動きについて深い洞察を持っています。この本では、脳がどのように進化してきたのか、そして私たちの思考や感情にどのように影響を与えるのかが丁寧に語られています。 科学的な知見を基にしながらも、一般の人にもわかりやすく解説されているため、誰でも楽しめる内容になっています。
-

けもの道の歩き方/千松信也
¥1,400
出版:リトル・モア 発売:2015年 定価:1760円 384ページ ================== 『ぼくは猟師になった』で狩猟ブームの先駆けを担った著者による新刊! - - - ・昭和の里山は理想郷だったのか? ・人里に動物が出没するのは森の荒廃が原因か? ・自然は「手つかず」が理想か? ・自然はカラダにいいのか? ・猟師は森の番人か? ・猟ができるのは山間部の人間だけか? - - - 狩猟採集生活の中で練り上げた、現代猟師考。 野生動物たちと日々行き交い、これからの自然を思う、20のエッセイ。
-

料理の四面体/玉村豊男
¥500
出版:中央公論新社 発行:2010年 定価:713円 10.5 x 1.2 x 15 cm・259ページ ======================================== 「すべての料理は四面体で説明できる! 」 料理本にして論理的思考が学べる奇跡の書。(原著1980年) 英国式ローストビーフとアジの干物の共通点は? 刺身もタコ酢もサラダである? アルジェリア式羊肉シチューからフランス料理を経て、豚肉のショウガ焼きに通ずる驚くべき調理法の秘密を解明する。火・水・空気・油の四要素から、全ての料理の基本を語り尽くした名著。
-

ぼくは猟師になった/千松信也
¥600
出版:リトルモア 発行:2008年 定価:1600円+税 ソフトカバー・224ページ ================== 京都に住む33歳の若き猟師による書き下ろしエッセイ。 著者の千松信也は何を思い猟師になったのだろうか。 幼少期の思い出や山での暮らしを淡々と語る一方で、 現代の食肉に対する考えや自分の在り方、人の在り方について 明解且つシンプルに綴る。 「地球の裏側から輸送された食材がスーパーに並び、 食品の偽装が蔓延するこの時代にあって、 自分が暮らす土地で、他の動物を捕まえ、殺し、 その肉を食べ、自分が生きていく。 その全てに関して責任があるということは、 とても大変なことであると同時にとてもありがたいことだと思います」 (本文より抜粋) そのほか、千松さんが行う「ワナ猟」と呼ばれる狩猟方法、 獲物の解体やワナのメカニズムを写真と図で詳細に解説。 猟師によるおいしい肉料理のレシピも掲載。 猟師の一年間に密着できる一冊。
-

鳥類学者無謀にも恐竜を語る/川上和人
¥500
出版:新潮社 発行:2018年 定価:825円 文庫サイズ・427ページ ================== 少年から大人まで楽しめる、絶品科学エッセイ はじめに 鳥類学者は羽毛恐竜の夢を見るか 序 章 恐竜が世界に産声をあげる 第1章 恐竜はやがて鳥になった 第2章 鳥は大空の覇者となった 第3章 無謀にも鳥から恐竜を考える 第4章 恐竜は無邪気に生態系を構築する あとがき 鳥類学者は羽毛恐竜の夢を見たか? 文庫版あとがき、あるいは鳥がもたらす予期せぬ奇跡
-

物理学と神/池内了
¥500
出版:集英社 発行:2002年 定価:1100円 新書サイズ・256ページ ================== 「神の御技」か?物理的な現象か?神の姿の変容と自然観・宇宙観の変遷をたどる刺激的な物理学入門 「神はサイコロ遊びをしない」と、かつてアインシュタインは述べた。それに対し、量子論の創始者ハイゼンベルグは、サイコロ遊びが好きな神を受け入れればよいと反論した。もともと近代科学は、自然を研究することを、神の意図を理解し、神の存在証明をするための作業と考えてきたが、時代を重ねるにつれ、皮肉にも神の不在を導き出すことになっていく。神の御技と思われていた現象が、物質の運動で説明可能となったのだ。しかし、決定論でありながら結果が予測できないカオスなど、その後も神は姿を変えて復活と消滅を繰り返し、物理学は発展し続けている。神の姿の変容という新しい切り口から、自然観・宇宙像の現在までの変遷をたどる、刺激的でわかりやすい物理学入門。 [著者情報] 池内 了 (いけうち さとる) 一九四四年兵庫県生まれ。京都大学理学部物理学科卒業。同大学大学院理学研究科物理学専攻博士課程修了。名古屋大学大学院理学研究科教授。『泡宇宙論』『観測的宇宙論』『科学の考え方・学び方』『天文学と文学のあいだ』『科学は今どうなっているの?』『私のエネルギー論』『天文学者の虫眼鏡』など、著書多数。講談社出版文化賞、産経児童出版文化賞などの受賞歴がある。
-

単純な脳、複雑な私/池谷裕二
¥1,100
出版:講談社(ブル-バックス) 発行:2013年 定価:1430円 11.3 x 2 x 17.4 cm・480ページ ======================================== 「心」はいかにして生み出されるのか? 最先端の脳科学を読み解くスリリングな講義。 ベストセラー『進化しすぎた脳』の著者が、母校で行った連続講義。私たちがふだん抱く「心」のイメージが、最新の研究によって次々と覆されていく──。「一番思い入れがあって、一番好きな本」と著者自らが語る知的興奮に満ちた一冊。
-

ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑/柴山元彦
¥1,400
出版/創元社 発行/2015年 定価/1650円 12.9 x 1.3 x 18.9 cm・159ページ ================== ルビー、サファイア、ガーネット……。 憧れの鉱物や宝石は、じつは近くの川原や海辺で簡単に見つけられるのをご存知ですか? 本書は、水辺で見つかる色とりどりの鉱物・宝石を、 見比べやすい原石のままの姿で紹介する、まったく新しい石さがしガイドブックです。 鉱物図鑑やアクセサリーでは、 よく磨かれて発色もよい美しい結晶を目にすることが多いと思いますが、 実際に川原や海辺で見つかる時には、ひと目でそうとはわからないような 石や粒であることがほとんど。 母岩を割ってみたり、川砂利を漉してみたり、 磁石で集めてみたり…見つけ方にもコツが必要です。 本書では、著者が長年の石探しの経験を活かして、 石探しをしやすい全国23ヶ所のスポット地図つきで紹介。 各スポットごとに、見つかりやすい鉱物や探す際のポイントを丁寧に解説しています。 鉱物の写真は、そのほとんどを拾った時のままの姿で掲載し、 実際の石探しでも比較して参考にできるようになっています。 第一巻では、川原や海辺で見つかる代表的な鉱物34種の図鑑に加え、 集めた鉱物の見分け方や、そもそも鉱物がどのようにできるのかという地学講座、 持ち帰った石の磨き方まで、石探しの基礎を徹底解説しています。
-

宇宙のはじまり/多田将
¥600
出版:イースト・プレス 発行:2015年 定価:760円+税 新書サイズ・192ページ ================== なぜ人間は宇宙に存在するのか? 人気の素粒子物理学者が物質の起源に迫る120分の超絶講義。 宇宙はどのように誕生し、今の姿になったのか? 140億年後を生きる人類は、加速器という装置を作り出し、宇宙が生まれた瞬間――100兆分の1秒後にまで迫っている。なぜそんなことができるのか、人気素粒子物理学者がその仕組みをわかりやすく解説。ラーメンをフーフーする理由とは? マカダミアナッツチョコのナッツだけを人類は食べることができない? スキーに行った修学旅行生は夜、何をしているのか?――宇宙誕生の謎を巧みな比喩と共に描き出す。
-

京大総長、ゴリラから生き方を学ぶ/山極寿一
¥450
出版:朝日新聞出版 発行:2020年 定価:660円 文庫サイズ・208ページ ================== 世界的なゴリラ研究者であり、京都大学総長によるグローバル時代を生き抜くための発想術。「精神的な孤独が、自信につながる」「他人の目が〈自分〉をつくる」「他人の時間を生きてみる」など。学生、新社会人必読の一冊。
-

数学の歴史物語/Jonny Ball
¥1,200
出版/SBクリエイティブ 発行/2018年 定価/2700円+税 13.3 x 3 x 18.9 cm・512ページ ================== 数学は、どのように歴史を変えたきたか? 抜群のストーリーテリングで綴られる壮大な数学ヒストリー。 古代から近代までのさまざまな数学者を取り上げて、彼らの業績を紹介した本です。彼らが生み出した数学的内容とともに、その数学が生まれた時代背景や、その数学がきっかけとなって起こった科学や技術の発展、ひいては歴史に与えた影響を紹介しています。数学の発展を通して見た世界史の解説書ともいえます。 文章は読みやすく、難しい数式はほとんどありません。歴史的に重要な図版やイラストも多数収録しています。ことに16ページにわたるカラー口絵は、多くの読者を魅了するでしょう。 数学や世界史に関心のある方はもちろん、面白い読み物を読みたいという一般読者にとっても最適な一冊です。
-

セミたちと温暖化/日高敏隆
¥300
出版:新潮社 発行:2007年 定価:476円+税 文庫サイズ・213ページ ================== 東京では珍しかったクマゼミの声を、最近よく聞くようになった。虫好きは喜ぶが、ことはそう単純ではない。気温で季節を数える虫たちが、温暖化で早く成長する。しかし日の長さで春を知る鳥たちは、子育て時期を変えられない。餌が少なくて親鳥は大ピンチ。ひたひたと迫る温暖化の波に、生き物たちはどういう影響を蒙っているのか? 自然を見つめる優しい目から生れた人気エッセイ。
-

形の生物学/本多久夫
¥550
出版/NHK出版 発行/2010年 定価/1400円+税 12.9 x 1.8 x 18.2 cm・372ページ ================== ヒトとサル、イヌとネコ、エビとカニ、ウニとヒトデ・・・・・・。生物は、今ある形にどうやってたどり着いたのだろう。神が決めたのか、遺伝子が決めたのか。本書では多細胞動物の袋構造に注目し、細胞が情報や指示書がないままに形を形成する自己構築・自己組織化の力から生物の形作りを論じる。進化を形の多様性の視点から解き明かし、生物学の新たな1ページを開く。
-

鳥類学者だからって鳥が好きだと思うなよ/川上和人
¥500
出版/新潮社 発行/2017年 定価/1190円 単行本(ソフトカバー)・224ページ ======================================== 鳥類学者に必要なのは、一に体力、二に体力、三、四がなくて、五に体力?! 出張先は火山に、ジャングル、無人島……!? 耳に飛び込む巨大蛾、襲い来るウツボと闘い、吸血カラスを発見したのに、なぜか意気消沈し、空飛ぶカタツムリに想いをはせ、増え続けるネズミ退治に悪戦苦闘する――。 アウトドア理系「鳥類学者」の知られざる毎日は、今日も命がけ! センセイ、ご無事のお戻り、祈念しております……(担当編集者) はじめに、或いはトモダチヒャクニンデキルカナ 第一章 鳥類学者には、絶海の孤島がよく似合う わざわざ飛ぶ理由がみつかりません/火吹いて、地固まる/最近ウグイスが気にくわない/帳と雲雀のあいだに 第二章 鳥類学者、絶海の孤島で死にそうになる 南硫黄島・熱血準備編/南硫黄島・死闘登頂編 第三章 鳥類学者は、偏愛する 筋が通れば因果は引っ込む/それを食べてはいけません/赤い頭の秘密/カタツムリスティックワンダーランド 第四章 鳥類学者、かく考えり コペルニクスの罠/二次元鳥類学事始め/冒険者たち、冒険しすぎ/シンダフルライフ 第五章 鳥類学者、何をか恐れん 熱帯雨林の歩き方/エイリアン・シンドローム/となりは何をする人ぞ/恐怖! 闇色の吸血生物 第六章 鳥類学者にだって、語りたくない夜もある 素敵な名前をつけましょう/非国際派宣言/林檎失望事件/ダイナソー・イン・ブルー おわりに、或いはカホウハネテマテ
-

ご冗談でしょう、ファインマンさん(上)/R・P・ファイマン
¥500
出版/岩波書店 発行/2000年 定価/1100円+税 文庫サイズ・343ページ ================== R.P.ファインマンは1965年にJ.S.シュウィンガー、朝永振一郎とともにノーベル物理学賞を授賞した天才的な物理学者である。こう書くと「理数系が苦手」な人は逃げ出したくなるかもしれないが、そんな人にこそ本書を手にとっていただきたい。 本書は20世紀を代表する天才物理学者の自伝ではない。R.P.ファインマンという人生を楽しむ天才から我々への贈りものである。 「ファインマンと聞いたとたんに思い出してもらいたいのは、ノーベル賞をもらったことでもなければ、理論物理学者であったことでもなく、ボンゴドラムでもマンハッタン計画でもない。僕が好奇心でいっぱいの人間であったということ、それだけだ」といつも言っていた(下巻訳者あとがきより)。 「なぜだろう?」といつも好奇心いっぱいの子どものように世界を見て、いったん好奇心をひかれたらそれに夢中になり納得のいくまで追求する。彼は一切の虚飾と権威を嫌い、相手がそれをかさに着ているとみるや容赦しなかった。それは、そのような態度が、楽しいはずの真実の探求を邪魔する厄介なものだったからである。 上巻では、彼の少年時代、物理学者としての修行時代、また駆け出しの物理学者として携わったマンハッタン計画から終戦を迎えるころまでのエピソードが収録されている。どの時代においても彼はその状況を最大限楽しみ、そして、決して流儀を変えなかった。 自分が理系か文系かなんて関係ない。もし少しでも本書に「好奇心」を持ったなら、ぜひ一読をおすすめする。(別役 匝)
-

ご冗談でしょう、ファインマンさん(下)/R.P.ファイマン・大貫昌子訳
¥500
出版/岩波書店・岩波現代文庫 発行/2000年 定価/1300円 文庫サイズ・327ページ ======================================== 20世紀アメリカの独創的物理学者が、奇想天外な話題に満ちた自らの体験をユーモアたっぷりに語る。持ち前の探求心と、大のいたずら好きは少年時代から変わらぬまま。大学時代や戦時下の研究所生活でも、周囲はいつもファインマンさんにしてやられる。愉快なエピソードのなかに、科学への真摯な情熱を伝える好読物。
-

世界のヘンな研究/五十嵐杏南
¥800
出版:中央公論新社 発売:2023年 定価:1760円 ソフトカバー・256ページ ======================================== テーマパークやカジノ、大麻など、日本に住んでいると不思議に思うユニークな授業が、世界にはたくさんある。本書は、サイエンスライターとして世界各国の科学関連のニュースに触れる著者による、「所変われば学びも変わる」異文化事情を伝える1冊。 「所変われば品変わる」は研究の世界でも言えることで、世界は風変わりな学びにあふれている。当事者にとっては生活の当たり前の一部なのに、地域性があまりに強いが故に、外からしてみたらちょっとヘンなものがたくさんある。本書では、世界の各地域で、その地域だからこそ行われている学びの場について紹介する。 学びの中でも、地域ならではの娯楽や生活の中の楽しみに関わるものがある一方で、地域特有の課題を対処し、生き抜いていくために重要なものもある。さらに、その知識を受け継いでいくために、独特な授業で教えることもある。そんな一面にももれなく着目していきたい。 世界は狭いようで広い――本書で登場するのは、世界のヘンなお勉強のほんの一握りのはず。軽くかじるくらいのゆるい気持ちで、お楽しみください。
-

一晩置いたカレーはなぜ美味しいのか/稲垣栄洋
¥350
出版:新潮社 発行:2022年 定価:605円 文庫サイズ・240ページ ======================================== 身の回りの食材には、さまざまな「謎」がある。 トウガラシはなぜ辛くて赤いのか? ニンニクはどうして健康にいいのか? メロンにはなぜ網目があるのか? そして、そんな食材たちが使われる料理にもたくさんの「謎」が隠されている。 一晩置いたカレーはなぜおいしいのか? 子どもたちはどうしてピーマンが嫌いなのか? スポンジケーキが膨らむ理由は? これらの謎を解くカギは、食材が生きていたときの姿にあった。本書では、野菜や肉、魚などの生き物としての特徴を手掛かりに、食材や料理の謎を、科学的に解き明かしていく。併せて、ジャガイモを煮崩れさせない方法や、泣かずにタマネギを切る方法など、調理の裏ワザも多数紹介。料理や食事が楽しくなる「おいしさの秘密」をご賞味あれ。 解説は、スパイス料理研究家の印度カリー子さん。
-

雑草キャラクター図鑑/稲垣栄洋
¥800
出版/文春文庫 発行/2017年 定価/1760円 ソフトカバー・215ページ ======================================== 『雑草手帳』などで知られる著者が おなじみの身近な雑草約70種をキャラクター化 散歩中の雑草を見る目が変わります! 雑草のユニークな生き方を紹介してきた著者初のキャラクター図鑑。 都会でよく見かける雑草を、その性格や生存戦略をもとに大胆に擬人化しながらわかりやすく解説しました。 「スター性アリ」「実は性悪」「知性派」「悪役気質」などなど、各植物をキャラの特徴で章立てしている新感覚の図鑑です。 雑草の世界を新しい視点で眺めてみると、実は都会ぐらしや競争社会の人間が参考にしたい世渡り術がいっぱい。 自分に似ているキャラを見つけると、人生をしたたかに、そしてしなやかに生きるヒントが得られるかもしれません。
-

植物は知性を持っている/ステファノマンクーゾ+アレッサンドラ・ヴィオラ
¥800
出版:NHK出版 発行:2015年 定価:1980円 ハードカバー・232ページ ================== 人と違うのは「動かない」ということだけ 植物学の第一人者が初めて明かす驚愕の知的世界。植物は、人間と同じく“予測"し、“学習"し、“記憶"し、仲間どうしで“コミュニケーション"をとっている。つねに鋭い感覚で情報分析し、生き残り戦略を“考えている"のだ。最新研究が突き止めたその真の姿を知れば、畑の野菜も観葉植物も、もう今までと同じ目では見られなくなる。『雑食動物のジレンマ』の著者マイケル・ポーランの序文付き。
-

春の数え方/日髙俊隆
¥300
出版:新潮社 発売:2005年 定価:400円+税 文庫サイズ・240ページ ================== 春が来れば花が咲き虫が集う──当たり前? でもどうやって彼らは春を知るのでしょう? 鳥も植物も虫も、生き物たちは皆それぞれの方法で三寒四温を積算し、季節を計っています。そして植物は毎年ほぼ同じ高さに花をつけ、虫は時期を合わせて目を覚まし、それを見つけます。自然界の不思議には驚くばかりです。日本を代表する動物行動学者による、発見に充ちたエッセイ集。
-

生物と無生物のあいだ/福岡伸一
¥400
出版:講談社 発売:2007年 定価:740円+税 新書サイズ・286ページ ================== 生命とは、実は流れゆく分子の淀みにすぎない!? 「生命とは何か」という生命科学最大の問いに、いま分子生物学はどう答えるのか。 歴史の闇に沈んだ天才科学者たちの思考を紹介しながら、現在形の生命観を探る。
-

サイエンス異人伝/荒俣宏
¥550
出版:講談社(ブルーバックス) 発売:2015年 定価:1280円+税 386ページ ================== かつて、電気から電波、エレクトロニクスへと発展していくにつれて消え去った「実体」が、21世紀になって、「科学家電」と呼ぶべきスマホなどの登場でよみがえり、科学が「手触り」の世界に戻ってきた。科学がふたたび人間と機械を通して語られ、未来の科学はもはやSFではなくなった。20世紀に突如として現れた発明品と発明者の伝記を読み解くことで、いままた現代科学が「素人にも理解できる」機械と人間からなる実体(リアル)へと変わる。